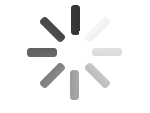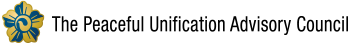[国内] 機関紙「平和統一」 第217号 『「分断の最前線 接境地域の住民が語る変化 接境地域のいま」、拡声器の音が止むと聞こえてくる暮らしの物語』
- メディアコミュニケーション課
- 2025-07-01 ~ 2025-08-01
機関紙「平和統一」 第217号 『「分断の最前線 接境地域の住民が語る変化 接境地域のいま」、拡声器の音が止むと聞こえてくる暮らしの物語』
対北・対南拡声器放送が中断してから2か月、接境地域の住民はようやく静かな夜を取り戻しました。しかし、緊張が完全に消えたわけではありません。戦車や大砲の音、汚物風船、対南放送の轟音は、依然として住民の生活の奥深くに刻まれています。
民主平統は、接境地域を代表する江華・金浦・鉄原の住民を招き、彼らの暮らしに刻まれた分断の現実と平和の意味を問う座談会を行いました。この座談会には、▲チョン・ヨンソン建国大学教授(司会)、▲キム・ギョンホ江華島キムチ代表(仁川・江華郡)、▲チョ・ミンジェ金浦歴史文化研究所所長(京畿・金浦市)、▲シン・ヘジョン接境地域住居環境研究所所長(江原・鉄原郡)が参加しました。
まとめ:チョ・ウンギョム 写真:パク・チャンス 映像:チェ・ウィイン
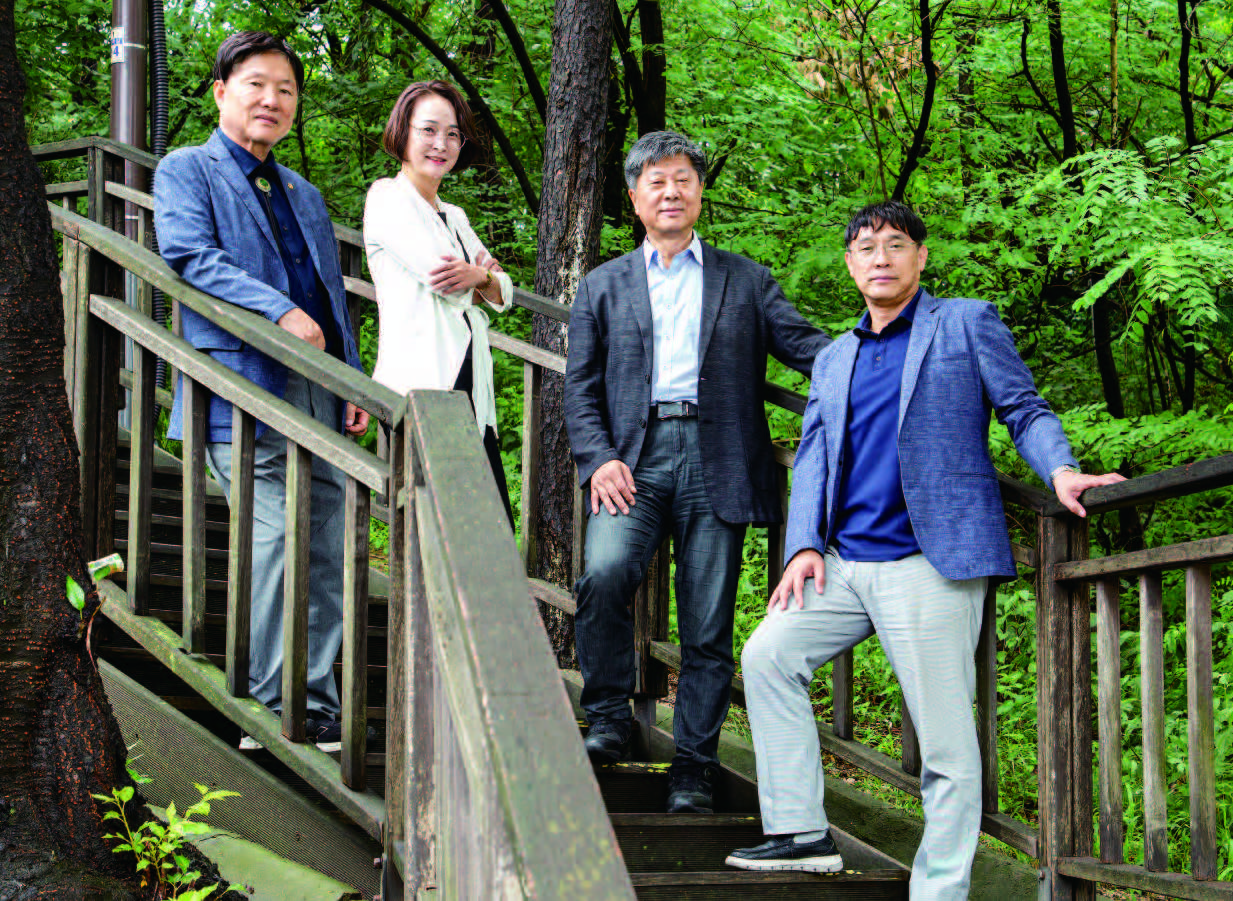
司会:チョン・ヨンソン
・建国大学統一人文学研究団・教授
・第13、15〜21期諮問委員、常任委員
討論
キム・ギョンホ(仁川・江華郡)
・江華島キムチ代表
・第18〜21期諮問委員、第21期協議会長
チョ・ミンジェ(京畿・金浦市)
・金浦歴史文化研究所所長
・第18〜21期諮問委員
シン・ヘジョン(江原・鉄原郡)
・接境地域住居環境研究所所長
・第19〜21期諮問委員
戦車や大砲の音を鳥のさえずりのように聞いていた子ども時代
司会:まず、接境地域で暮らしてこられた経験を中心に、自己紹介をお願いします。
シン・ヘジョン:私は鉄原で生まれ育ちました。幼い頃の私の日常は、いつも戦車や大砲の音でいっぱいでした。夜になると、明かりが一筋も漏れないように統制され、耳の中で響き渡る対南放送が空気のように流れていました。ソウルでしばらく暮らした後に再び鉄原に戻ってきたとき、静かな夜の空気がどれほど異質だったことか……。鉄原は昼と夜でまるで違います。昼は戦車が道路を塞いで通過し、大砲の音で建物が揺れることもあります。子どもたちは、その音をまるで鳥のさえずりのように聞きながら育ってきました。
チョ・ミンジェ:私は金浦で育ちました。子どもの頃の一番の思い出は、ビラ拾いです。金浦は三方を鉄柵に囲まれた地域です。都市化が急速に進んでその感覚は薄れましたが、郊外に出ればいつでも鉄柵を見ることができます。ここに暮らす人々は、常に分断の現実を抱えて生きています。
キム・ギョンホ:江華は自然豊かな農業地域であり、観光地です。南北関係が悪化すると、真っ先にその影響が現れる場所でもあります。農繁期に車両移動が制限されると、肥料の運搬が難しくなり、農家が大きな経済的被害を受けることになります。ここの住民は軍事的緊張が高まるたびに、「今度は何が起こるのだろう」という心配をします。
平凡な日常を壊した汚物風船と対南放送
司会:ここ1年の間に、北朝鮮の汚物風船や対南放送が住民に直接的な被害を与えました。実際に経験されたことはありますか。
シン・ヘジョン:私の町では、田んぼに汚物風船が落ちました。ごみ袋が破れていて、農業用の機械を使って片付けましたが、その後大きな不安を感じる日々が続きました。地元の人たちは、対南放送のことを「幽霊の声」と呼んでいます。周りには唸る音で不眠症に悩まされた人も多く、食堂の前に風船が落ちて丸1日営業ができなかったという方もいます。
チョ・ミンジェ:金浦は人口が50万人に達する大都市に成長していますが、それでも汚物風船への不安がないわけではありません。金浦空港の近くでは、自動車部品工場に風船が落ちて火災が発生したこともあります。このように、汚物風船は住民の安全を脅かすものとなっています。
明け方に響き渡る対南放送の音は幽霊の声のようでした。子どもたちは眠れず、家畜は飼料を食べたがりませんでした。

キム・ギョンホ江華島キムチ代表
キム・ギョンホ:江華の被害は最も甚大でした。毎日明け方に聞こえてくる対南放送の音で住民は眠れず、不安から病院を受診する子どもも多かったです。家畜も轟音に驚いて飼料を食べなくなり、農家は大きな被害を受けました。一部の家庭に防音装置が設置されましたが、住民全体を守るにはあまりにも不十分でした。
対南放送が止まり、取り戻した静かな夜
司会:新政権の発足以降、最も顕著な変化の一つが対南放送の中断です。南北関係改善のモメンタムにつながるのではという期待の声も聞かれますが、実際に感じた変化はありますか。
キム・ギョンホ:大統領の就任直後、私たちが放送を中断すると、北朝鮮の放送もすぐに止まりました。その瞬間、町はたちまち平穏を取り戻しました。以前は放送のせいで入院した人もおり、苦情が絶えなかったのですが、音が消えると同時に苦情も大幅に減りました。町全体の雰囲気が変わったと思います。
接境地域の協議会同士が交流し、連帯して活動していくことが必要です。小さなイベントでも続けていくことが、平和の火種を守ることにつながると思います。

チョ・ミンジェ金浦歴史文化研究所所長
チョ・ミンジェ:今の平穏がこれからも続き、南北が平和的に交流し、意思疎通できるきっかけになってほしいです。一時的な変化ではなく、持続する平和の流れとして定着することを願っています。
シン・ヘジョン:鉄原では、対南放送が止まると同時に、わずか1年前は当たり前だった不安な日常が一瞬にして正常なものに戻りました。心の落ち着きと安定を取り戻したことで、何よりもよく眠れるようになりました。それが一番大きな変化です。農家では、早朝の午前4時から1日の仕事を始めます。会社員とは生活パターンが違うので、夜8〜9時には就寝しなければなりません。しかしその時間に対南放送が絶え間なく聞こえてくるので、まともに眠ることができませんでした。でも今は、何の音も聞こえず、寝たいときに寝られるし、目覚めたいときに目覚められます。そのおかげで心身ともにエネルギーが満ちあふれ、正常な日常が送れるようになりました。これこそが、住民たちが感じる最大の平和ではないでしょうか。
接境地域は規制と機会の土地
3人の討論者は口をそろえて、接境地域の自然環境と歴史・文化資源を大きな資産として挙げた。しかし同時に、軍事保護区域、開発制限、道路インフラ不足などによって発展が制約されていると指摘した。
司会:接境地域で暮らすメリットは何でしょうか。また、それが地域発展や南北関係の変化にどのような影響を与えると考えますか?
チョ・ミンジェ:金浦は豊かな文化遺産と地理的な利点を備えています。しかし、鉄柵や各種規制により、その活用が難しい状況にあります。歴史資源を物語化し、交流の拠点として発展させていくために、政策的な支援が必要です。
シン・ヘジョン:鉄原は広大な農地を有していますが、道路が整備されていないため、農産物の運搬が困難です。住民の生活基盤を安定的に支えるためには、交通網の拡充が何よりも必要です。
キム・ギョンホ:江華の強みは、よく保存された自然環境と農業に適した土壌です。また、軍事境界線に近いことから、歴史や安全保障に関連する観光資源が多く、観光産業の潜在力が高いです。しかし、人口流出と高齢化が急速に進み、地域の活力が失われつつあります。地域特産物の販売・加工施設を拡充し、若者の流入を促進して、定住環境を改善する必要があります。

内部対立の傷を癒す最善策は「教育」と「体験」
司会:最近、韓国社会では「南南対立」「男女対立」という表現が日常的に使われるほど、社会の分裂が深刻化しています。国内において和解と理解を促進するために、何ができるでしょうか。
キム・ギョンホ:海辺に沿って続く鉄柵区間を散策路として整備すれば、住民たちにとって競争心ではなく、平和と連帯を体感できる場所になるのではないかと思います。以前、江華でウォーキング大会を開催したことがありますが、政府や自治体がもう少し力を入れてくれれば、地域住民が自然に交流できる機会が増えると思います。
シン・ヘジョン:かつては「私たちの願い」という歌を無意識に口ずさみながら育ちましたが、今の学生たちは、分断や統一といった概念について、私たちの世代に比べてあまり馴染みがないように思います。子どもたちには、直接民間人統制線の内側に入り、現場を体感する経験が必要だと思います。そのためにも統一教育を学校の必修科目にし、政府や自治体が安全な体験プログラムを体系的に提供していく必要があると思います。
チョ・ミンジェ:金浦は平均年齢が40代前半の若い都市で、住民の90%以上が外部から流入した人々です。こうした環境では、前世代的なイデオロギー教育は効果的とは言えません。青少年を中心に家族で参加できる平和・安全保障プログラムが必要だと思います。金浦章陵や鉄柵区画周辺には歴史的資源が豊富にあります。漢江と臨津江がひとつであった時代を思い起こし、その意味に共感できれば、統一の必要性も、平和・交流・協力の必要性も自然と理解できるようになるでしょう。
「平和ヌリ道」から「協力の道」まで
司会:地域住民が持つ資源や価値を媒介として互いに触れ合いながら、平和統一へとつなげていくことが必要だということですね。ところで自治体のレベルで、こうした流れを支えるための具体的な政策や取り組みは用意されているのでしょうか。
チョ・ミンジェ:金浦は都市化が急速に進み、接境地域としての特性が薄れつつあります。かつては開城工業団地のような南北交流の拠点もありましたが、現在は鉄道問題など首都圏の懸案事項が優先課題となっている残念な状況です。政権が変わるたびに政策の方向性が変わるのも制約要因です。地域レベルでできることは続けていますが、どうしても限界があります。
キム・ギョンホ:江華には喬棟のような広大な土地があります。そこに工場を建て、将来的には北朝鮮の人々とともに暮らすという構想も考えられるのではないでしょうか。土地の保存という考え方を超えて、南北が共に活用し、共に繁栄できる空間をつくっていく必要があると思います。
チョ・ミンジェ:民主平統の諮問委員たちは、過去10年以上にわたり「平和ヌリ道」を中心にキャンペーンやイベントを行ってきました。金浦では、鉄柵の下の壁に壁画を描き、市民の皆さんにとって平和の意味を体感できる空間を提供しています。また、北朝鮮離脱住民や多文化家庭のためのイベント、地域探訪プログラム、ボランティア活動も継続的に行っています。金浦・江華・坡州からソウル江西区までを結ぶエリアには、ひとつの文化エリアとして共有できる資源が多く存在しています。民主平統がこれを積極的に媒介することで大きな成果を生み出せると考えています。
以前、釜山蓮堤区が相互訪問で金浦を訪れたことがありますが、参加者はみんな「北朝鮮とわずか1.4キロメートルしか離れていない」という事実に大変驚き、分断の現実を実感した様子でした。同じ接境地域でも雰囲気が異なるので、鉄原・江華・漣川など接境地域の協議会が相互に訪問し、活動を共有することの意味は大きいと思います。
シン・ヘジョン:鉄原では、DMZマラソン大会や音楽フェスティバルが開かれています。しかし、協議会レベルで連携して推進している事業はまだ少ないのが実情です。坡州の臨津閣から出発し、鉄原の中間地点まで歩くウォーキング大会を共催したことがありますが、このように接境地域の協議会同士が力を合わせてイベントを共同で実施し、成果を分かち合うことが今後の課題だと思います。

地雷がなくなり、子どもたちが平和の価値を学ぶ未来
司会:接境地域の住民として、南北関係について期待するところをお聞かせください。
キム・ギョンホ:江華・金浦・鉄原の3地域の協議会が集まって話をすると、結局いつも対北放送中断の必要性が話題になります。それほどまでに接境地域の住民は大きな苦痛を味わっているのです。日常生活への被害は日に日に拡大しています。政府と自治体には、真剣に検討してもらいたいと思います。民主平統には、和解と団結の雰囲気を醸成しつつ、地域の声をしっかり届けてくれることを期待しています。
チョ・ミンジェ:みんな同じ思いだと思います。南北関係が改善し、平和交流が活発になることを長らく期待してきました。しかし、政府のレベルで私たちの思いどおりに簡単に事が進むかというと、そうはならないでしょう。だからこそ、地域協議会のレベルで具体的な行動を行い、平和を守る意思を示す必要があると思います。諮問委員たちが連帯し、活動をメディアや中央に発信してはじめて、政府に住民の思いを届けることができると思っています。すぐに大きな政策変化を起こすことは難しくても、地域が主体となって実践的な活動を地道に継続していくことが大切です。
シン・ヘジョン:鉄原では最近、北朝鮮へのビラ散布を防ぐために行政命令と取り締まりを強化しました。疑わしい車両の流入を阻止し、住民の不安を軽減するなど、前向きな効果が出ています。しかし何よりも大切なのは、「戦わずして平和を実現する道」だと思います。現実的には予算が壁となっていますが、接境地域の協議会同士が力を合わせてイベントを共同で実施し、北朝鮮がすぐ近くにあるということを発信していくことが必要です。そして、子どもたちを丁寧に教育していくことが重要です。北朝鮮を直接見て体感し、平和の価値を学ぶ経験を通じて、子どもたちの関心と共感を高めることができますし、それがやがて彼らが築いていく未来にもつながることでしょう。
子どもたちへの教育を通じて北朝鮮を直接見て体感できる機会を提供することが必要です。民主平統がその役割を担うべきです。

シン・ヘジョン接境地域住居環境研究所所長
今日の日常から明日の希望へ
今回の座談会で語られた接境地域の住民たちの話は、地域の声を伝えることを超えて、韓半島の平和と統一という時代的課題を改めて思い起こさせるきっかけになりました。戦車や大砲の音に毎日耐えてきた世代、汚物風船や拡声器の騒音の中でも健気に暮らしてきた住民たちにとって、平和とは、自分とは関係のない巨大な議論ではなく、「今日の日常」であり「明日の希望」でした。彼らは、平和とは安心して眠れる夜であり、子どもたちが恐れることなく走り回って遊べる町であり、分断の傷を超えて地域が共に繁栄できる道であると強調しました。また、民主平統が地域の多様な資源と住民の声をつなぐ架け橋となり、小さな活動でも地道に継続していくことが重要であることを明確にしました。
今回の座談会で示されたように、平和は今この場で実践し、築いていかなければならないものです。接境地域の住民の声が広がり、彼らの経験がみんなの共感と連帯へとつながったときに、韓半島は平和に向かってさらに一歩進むことができるでしょう。
-
ご覧になった情報に満足ですか?